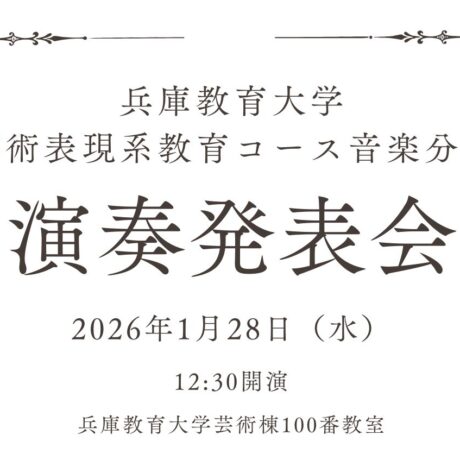器楽担当 教授(かわち いさみ)
担当授業
大学院:音楽表現の知識と技能Ⅲ(器楽)、音楽教育の創意Ⅲ(器楽)、音楽科授業の指導計画と教材研究の演習、初等音楽科教材研究授業づくり
学 部: 器楽演習Ⅰ&Ⅱ、合奏演習、初等音楽、音楽科教育法Ⅲ&Ⅳ、指揮法演習
自らの研究分野について
 専門はクラリネット。演奏に関しては、その技術や音楽表現についてはもちろんですが、レベルに応じた練習方法、特に基礎的訓練やその指導法を中心に研究しています。また、音楽科教育では教科書の器楽教材に対する教師の教材研究とそれを活かした指導助言を主な研究テーマとしています。合奏指導では、吹奏楽やオーケストラ、器楽合奏などの合奏指導法と基礎合奏についても精力的に取り組んでいます。さらに、アイ・トラッカー(非接触型視線分析装置)を用いた読譜時の視線分析や、音楽学習者の実行機能に関する研究も行なっています。
専門はクラリネット。演奏に関しては、その技術や音楽表現についてはもちろんですが、レベルに応じた練習方法、特に基礎的訓練やその指導法を中心に研究しています。また、音楽科教育では教科書の器楽教材に対する教師の教材研究とそれを活かした指導助言を主な研究テーマとしています。合奏指導では、吹奏楽やオーケストラ、器楽合奏などの合奏指導法と基礎合奏についても精力的に取り組んでいます。さらに、アイ・トラッカー(非接触型視線分析装置)を用いた読譜時の視線分析や、音楽学習者の実行機能に関する研究も行なっています。
ゼミ・研究室について
 ゼミは基本的に週に一度、院生も学部生も一緒に集まって行います(対面またはオンライン)。研究の進捗状況の報告や、問題点の発見、あるいは論文執筆のイロハなど、そこでの内容は様々です。特に院生の研究内容は、器楽分野に関わる題材ばかりでなく、広く音楽科教育全般に関わりのある題材を取り上げることも多く、柔軟な指導と自由な雰囲気を心がけています。フレックスクラスの院生の場合は、夜間に時間帯にオンラインを用いた指導となります。
ゼミは基本的に週に一度、院生も学部生も一緒に集まって行います(対面またはオンライン)。研究の進捗状況の報告や、問題点の発見、あるいは論文執筆のイロハなど、そこでの内容は様々です。特に院生の研究内容は、器楽分野に関わる題材ばかりでなく、広く音楽科教育全般に関わりのある題材を取り上げることも多く、柔軟な指導と自由な雰囲気を心がけています。フレックスクラスの院生の場合は、夜間に時間帯にオンラインを用いた指導となります。
音楽について思うこと、学生さんへ、そして自分へ。
 演奏会であれ、コンクールであれ、本番の演奏の善し悪しもさることながら、そのパフォーマンスに至る練習の過程、プロセスを大切にしてほしい、と常々考えています。俗に“音を楽しむ”などと安易に理解されがちですが、そんな甘いものではないと思う。他人からすれば『無駄』としか感じら れないほどの時間や努力の消費があって初めて本番は成り立つし、その張りつめた緊張感や集中力は経験した者にしか理解出来ないものです。いやむしろ、そういう者のみが“極み”を垣間見ることが出来る、と言えるのです。
演奏会であれ、コンクールであれ、本番の演奏の善し悪しもさることながら、そのパフォーマンスに至る練習の過程、プロセスを大切にしてほしい、と常々考えています。俗に“音を楽しむ”などと安易に理解されがちですが、そんな甘いものではないと思う。他人からすれば『無駄』としか感じら れないほどの時間や努力の消費があって初めて本番は成り立つし、その張りつめた緊張感や集中力は経験した者にしか理解出来ないものです。いやむしろ、そういう者のみが“極み”を垣間見ることが出来る、と言えるのです。
教師を目指す君たちには是非その感覚を身に付けた上で教壇に立ってほしい。実際の授業では、目の前にいる児童や生徒たちにそんなことを直接伝えることはたぶん無いでしょう。でも、うわべだけ、形だけ授業を進める教師との決定的な違いを子どもたちは必ず感じとっているはずです。
プロフィール
 京都芸術大学音楽学部卒業。インディアナ大学大学院修士課程およびパフォーマー・ディプロマ修了。14 年に及ぶアメリカ生活では、コロンバス・インディアナ・フィルハーモニック、テラホート・シンフォニーなど数々のオーケストラで首席クラリネットを歴任するとともに、ソロ・室内楽奏者としても活躍した。また、平成 11 年より 5 年間インディアナ州立大学音楽学部クラリネット科非常勤講師として後進の指導にもあたった。コンサート・アーチスト・ギルドなど種々のコンクールに上位進出を果たし、平成10年 9月には、松方ホール“松方音楽賞”において選考委員奨励賞を受賞した。帰国後、福岡県の県立高等学校教員を経て、平成22年より兵庫教育大学の教員となり現在に至る。
京都芸術大学音楽学部卒業。インディアナ大学大学院修士課程およびパフォーマー・ディプロマ修了。14 年に及ぶアメリカ生活では、コロンバス・インディアナ・フィルハーモニック、テラホート・シンフォニーなど数々のオーケストラで首席クラリネットを歴任するとともに、ソロ・室内楽奏者としても活躍した。また、平成 11 年より 5 年間インディアナ州立大学音楽学部クラリネット科非常勤講師として後進の指導にもあたった。コンサート・アーチスト・ギルドなど種々のコンクールに上位進出を果たし、平成10年 9月には、松方ホール“松方音楽賞”において選考委員奨励賞を受賞した。帰国後、福岡県の県立高等学校教員を経て、平成22年より兵庫教育大学の教員となり現在に至る。
また、日本木管コンクール理事や、MBSこども音楽コンクール西日本大会審査委員など数々の学外での活動も精力的に行なっており、令和2年には、論文の業績が評価され日本教育実践学会において『第3回 学会賞』も受賞した。
クラリネットをジェームス・キャンベル、アルフレート・プリンツ、ハワード・クルッグ、朝比奈千足、川崎大二郎の各氏に、オーケストラ奏法をエリ・イバン、室内楽をユージン・ルソー、吹奏楽指揮法をレイ・クレーマー各氏に師事。
![兵庫教育大学大学院 芸術表現系教育コース[音楽分野] 兵庫教育大学大学院 芸術表現系教育コース[音楽分野]](https://music.hyogo-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/wp-logo-music-1.png?1771788519)